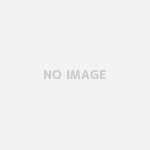TPPの議論が本格的になる前に、
参加表明が行われました (^_^)
まぁ、そうなるとは思っていましたが。
なんか、農業ばかりが取り上げられますね。
大事なことは他にもあると思うのですが。
一企業が、公正面から他の国を訴えることが出来るというのが
どうにも腑に落ちないですね。
それをやりそうなのが、アメリカベースの多国籍企業だけというのも。
勿論、対大陸をにらんでの、外交問題だということもあるのでしょうが、
それさえも、アメリカ国内の政治家に企業献金を降り注いでいる企業群の
本音を隠す手段かとも思ってしまう。
大風呂敷はこれくらいにして、農業問題。
これも、農業団体の保身問題と本質的な国内生産性の維持の問題がごっちゃになっている。
あ、また問題が大きくなってしまった。
そんなことより、
『歴史と風土』 司馬遼太郎さん
遊牧文化と古朝鮮より、
「稲作は一軒家ではできないのです。
大きな野原にぽつんと農家がありましたというような西洋のお伽話はできにくい。
里というものがないとだめなのです。
ひとつの里が水の問題で他の里と連携している。」
「大規模農場を作り、専業農家を厳選して、輸出ができるような体力を」
というふれこみの前に、
日本の米作りの状況がきちんと理解されていないですね。
里がないと、つまり、集団で住む人たちがいないと、
米作り、つまり、山の管理と水の管理は出来ないのです。
アメリカも豪州も、米作り農民は水の心配も世話もしません(と仄聞)。
国が面倒みてくれています。
しかも、その水は山から来ます。
山の管理をしているから、一年中、川に水が流れています。
不思議に思ったことはありませんか?
日照りでも、川に水があることを。
そして、農業、特に田んぼが水を使うからこそ、
山から海まで、水があるんです。
使うから、なくならない。
途中で水を使うことがなければ、
苦労してまで、山や里山や用水を管理しません。
経済学でいえば、外部経済だらけなんですね。
農民が自分たちのために米を作る、それが
環境を保護し、水を作り、山を守り、川を守ることにつながる。
そして、
地域に大規模農家や農場や企業が一つ残っても、
今まで村全体で行ってきた用水の管理などは
どうなるのでしょう?
自分たちで出来るのか、
出来なければ外国のように国が面倒みてくれるのか、
それはつまり、私たちの税金です。
ちょっとでも安い農産物を求めんがゆえに、
別の面で負担を強いられる。
しかも、その関連が見えない。
そういう根本的な問題が全く見えない状況ですね。