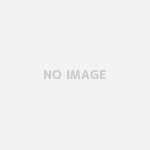以前の話ですが、大店法で量販店の規制をしてました。随分、変わって、今やほとんど規制もない状況。
消費者にとっては量販店の方が便利だから、消費者利益を考えれば別にいいんじゃいない?
自分も一人の消費者と しては、そう思う。昔の大店法って、政治屋が中小小売の票欲しさに出来もしないくせに「小売店の皆さんの立場を守ります」って宣伝するために存在してたんじゃないのだろうか。
以前、会社勤めでヨーロッパをぐるぐる出張で回った時にいつも感じたことだけど、街中が落ち着いていて、量販店もあるけど、小売もある。
そして、土曜日は半ドン、日曜日は休み、となんて不便。でも、小売だけは営業していた。
人口40万人のドイツの都市、デュッセルドルフ。街中には百貨店が二軒。そして、郊外に大きな市場。それだけ。
人口25万人の府中でも、17軒(だったか?)のス-パー がある。
デュッセルじゃ「何でもっとないのかいな?」と思ったけど、聞いてみたら、市民の代表で作った「街作り条例」みたいのがあって、量販店の数とか営業時間とかを規制している。
消費者としては量販店は便利だけど、生活者としてはそれ以外に考慮すべきことがあるので、自分達が暮らす自分達の町を総合的に判断している
、ということらしい。それを聞いて彼我の格差に嘆息!ついでに、自分の視野の狭さも、嗚呼!
府中市でも、市民の有識者を集めて「総合計画」なるものを作ってるけど、すべての項目がばらばら。
まさに総花的。
自然環境を守り、文化を高め、学校教育を拡充し、青少年健全育成に努め、防災対策を強化し、商店街を活性化し、生涯学習・スポーツの環境を充実し、地域の結びつきを再構築し、……。素晴らしい
「紙」。
すべてを横につなぐ物がない。
すべてそれぞれの担当部署が縦割りに仕事をし、それぞれに関わる市民もまた縦に割れている。実行主体であるべきの市民の覚悟はどこに?
結局、大した進展もないまま時は過ぎ、、何年か後には、行政として作成することになっているから、また新しい「総合計画」が出来るんだ。