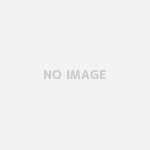「米すたいる」お米マイスターのチラシより
平安時代の末期は、それまでの貴族から武士に権力が移るなど歴史の大転換期。
その頃の武士の食事は、朝夕の1日2回食で、それも玄米飯ですから、よく噛む習慣が身につきます。よく噛むことによって、武士らしい精かんで鋭い表情と落ち着きが生まれました。
一方、貴族たちは精白した米のご飯。これを柔らかいご飯という意味で、「姫飯(ひめいい)」と呼びました。
当時の武士団の棟梁として大活躍していたのが、NHK大河ドラマの主人公である平清盛だったのです。頭脳力の鋭い清盛は魚を好み、とくにスズキが大好物だったようです。
清盛が若い頃、船に乗っていたらスズキが飛び込んできたので、早速料理して食べたところ運が向いてきたと「平家物語」にあります。
魚は”なます(現在の刺身)”にする場合が多く、タレは生味噌に酢を加えたもの。主食は米飯でおかずは魚、それに味噌汁と漬け物がつくのが武士流の健康食でした。
文:食文化史研究家 永山久夫
なお、この永山さんのウェブサイトがありました。
なかなか、強烈なキャラクターのようです。