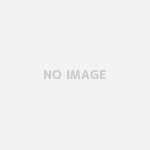どこまで続くか、このシリーズ。
防災の話しを前にしたけど、「消防団」ってご存知?ご近所に「~~市消防団第一分団」なんて書いた消防小屋を見たことは?
実は、火事に駆けつける消防車は、全部税金で賄っている消防署から来る車と、地域の人が自分の仕事を持ちながら半ばボランティアでやっている消防団の車の集合(半ば、というのは、一回の火事で3000円程度の出動費が出るから)。
府中の場合、一つの火事に(確か)5台の消防団車が出動する。
消防団の人は、仕事後に集まって放水や設備の訓練をしたり、冬場には交替で夜間の「火の用心」回りをしたり、勿論受け持ち区域で火災が発生すれば、昼夜を問わず消防小屋に駆けつけ消防車で出動する。
火事現場では、本職の消防署員が中心になって消火活動にあたるが、消防団も実際放水することもある。
楽器店が燃えた時など、消火できたと思ってもピアノの鍵盤(エナメル)が再発火することが続き、結局夜の12時頃の火事に対し現場を離れたのは明け方に なってから、ということも。
うちの前にあった八百屋さんで積んでいた段ボールに放火された時、市役所が街角に置いた消火器を使って消火したのも、飲みに出かけてた消防団員。
消防団員の構成員のほとんどが、小売商店・職人・農家。
要するに、これからさらに少なくなる人達。それで、震災後に良く言われる「災害に強い町」って、どんな町?
神戸の震災の朝、日本テレビ「ズームイン!!朝!」で、福留アナが叫んでいました。
「消防車が見えません、どこにいるんでしょう?」って、不満げに。
彼らは、本当に何も市民生活がわかっていないんでしょうね。それで、庶民の味方を気取っている。
結局、みんな、税金が作っている社会ってやつが、何でも面倒見てくれると思っている。
マスコミも行政の不手際なんかは追求するけど、市民の自助努力と か助け合いなんかは訴えない。衆愚だ。行政もハード面だけの防災対策。これだけやりました、っていう形式主義。
ちなみに、私は消防団員ではありません。