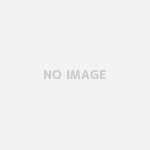日本の土壌は、この三十年の間にミネラルが半減しているらしい。
従って、野菜などから摂れるミネラル量も減っている。
亜鉛もその一例だが、亜鉛の場合、悪いことに摂取した量の3分の1程度しか体内に残らない、摂取効率の悪いミネラル。
食物の中の様々な物質が亜鉛と結びついて体外排出してしまう。
例えば、
カルシウム、食物繊維、タンニン・カフェイン、フィチン酸(豆類・穀類)、ポリリン酸(添加物)
などが、亜鉛の吸収を妨げる。
ポリリン酸以外は、日常の食生活で摂取する物で、亜鉛のことだけ考えて摂取しないようにできるものではない。
しかし残った亜鉛を3mg以上効率よく 吸収出来れば問題はなく、それを助けるのがクエン酸とビタミンC。
たとえば生カキやカキフライを食べるときにレモンをかけるのは利にかなった食べ方。
なお普通のお酢や柑橘類の酸っぱさの成分の多くは酢酸によるもので、酸っぱいもの=クエン酸が豊富というわけではない。
酢の中では黒酢が一番クエン 酸が豊富だそうだが、黒酢の良いところはエネルギーを生産する回路=「クエン酸サイクル」の中でクエン酸と同時に働く各種有機酸・ビタミン類が豊富に含ま れていることで、クエン酸の量だけ見れば、グレープフルーツなどの柑橘物がやはり多い。