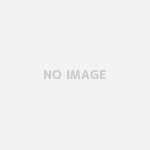白米に玄米を混ぜるのと
分搗きでは
どちらが栄養があるのか?
なんてご質問をいただいて。
勿論、
玄米の割合で変わってくるので、
こうだという答えはないのでしょうが。
ただ、
玄米や胚芽米、分搗き米は、白米に比べて
栄養があるので健康にいい
と良く言われることには違和感があります。
栄養があるのは当たり前です。
白米は、でんぷんとたんぱくだけと言っても過言ではないでしょう。
あとの微量要素のほとんどが
ヌカと胚芽にあります。
ほとんどないものと比べるのだから、
何倍、何十倍になっても当然。
本当に必要なことは、
各栄養素の一日の必要量に対して
玄米ならどの程度満たせるのかということ。
でも、こういうことはきちんと示されないんですね。
雑誌の記事やテレビの番組では、
「栄養がある玄米を食べましょう」という内容が
決まっていて、
それを援護するデータを
全体像を提示することなく部分的に見せる
ことに終始しますから。
具体的なデータは後日の宿題として、
一つ 過去のお米の消費量から考えてみましょう。
過去、一石(いっこく)とは150kg、
そしてそれが一人の人間を一年生かすのに必要な量。
加賀百万石とは、百万人を養える生産力を持つ、
もしくは、人口がそれより少なければ、
余剰分を大阪の市に出荷して、
現金収入を得ることが出来る藩だという意味。
閑話休題。
江戸時代、ほとんどの地域では、せいぜい分搗きの
お米を食べていたと思われます。
現在のような精白米は出来ませんから。
150kgも分搗き米を食べていても
江戸時代の日本人の体格は、
今から比べればはるかに小さい。
武士の平均的な食事では、
月に2~3回、魚を食べるくらい。
あとは、味噌汁と野菜。
やはり、
いくら栄養があるといっても
今のように年に60kg程度では、
とても足りませんね。
結局、
でんぷん・たんぱく・脂質・ミネラル・ビタミン
バランスの良い食事
ということになるのでしょうね。