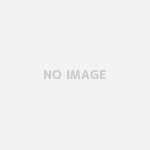今日も低グルテリン米のお問い合わせ。
低グルテリン米とは、タンパク質摂取の制限を受けている方へのヘルプとなるお米。
いつも、長い電話での説明の後に、「これでわかってもらえるか?」自問自答。
こんなんですが、どうでしょう?
1.
まず、タンパク質摂取のために、酵素処理したレトルト米(低タンパク米)が開発された。
病院の購買や通販で買える。
1/20とか1/25とか書いてある。つまり、タンパク質がそれしかないということ。
しかし、高くて不味い。
2.
そこで、開発されたのが、現在、低グルテリン米と呼ばれるお米。
最初は、低タンパク米とも呼ばれたが、
その後、厚労省と農水省の間で、タンパク質が半減しないのにこの名称はどうかという話になり、
低グルテリン米に変更。
グルテリンとは、体が吸収するタンパク質の一つで、これがお米のメインのタンパク質。
3.
低グルテリン米のポイントは、
体が吸収するタンパク質を減らしたこと。
お米は、デンプン質がメインだが、タンパク質も7%くらいある。
五訂日本食品成分表によれば、玄米100gに6.8gという「みなし」。
実際は、5~8%くらいにはぶれる。
このうち、75%くらいは体が吸収する易消化性タンパク質、
残りが吸収しない難消化性タンパク質。
ということで、
この易消化性を減らし、難消化性を増やせば、
結果として、体が吸収するタンパク質は減る、という仕組み。
品種により、また毎年の出来にもより、数値は変わるが、
だいたい、普通のお米の6割前後。
4.
そして、一番、お客様の知りたいことが、
「ご飯100gで、タンパク質は何グラム?」
ということ。
とにかく、摂取している食品のタンパク質を計算したいので、
当然の質問なんですが。
ここからが一番難しい。
1)まず、農産物は工業規格品のようには作れない。常にぶれがある。
2)そも、国の栄養成分も「みなし」であり、確か、タンパク質も20%くらいのぶれが認められている。
3)従い、絶対値は求められない。あくまで、参考値。全ての食品及び成分表示は、そういうものだと認識してください。
4)しかしながら、それでは、何も指標がないので、当店の過去十年近く仕入れてきたお米の分析結果からは、
「ごはん100gに、体が吸収するタンパク質は1.2~1.9g。勿論、理論的には、これ以上も以下もありうる。」
と説明しています。
また、栄養士さんが対象にしている数値は、タンパク質総量で、易消化性とか難消化性とかは、ほとんど認知されていないから、お客さんが医師や栄養士さんと話しても、なかなか通じないと思う。らちがあかない場合は、直接、医師・栄養士から電話がもらえるとありがたい。
ともお願いしています。
どうでしょうか?
これで、わかるでしょうか?
とにかく、薬ではないし、勘違いされてのお買い上げも困るし、という、
売っているのに、「買わないで」ともとれる説明の仕方になってしまいます (~_~;)